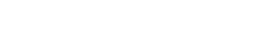- TOP
- 森林空間の活用を推進
森林空間の活用を推進
日本経済新聞社が有識者を招き、森林と企業の共創について考える会議「社会課題解決の切り札となる森林」。その第2回会合が10月31日に東京都内にて開催された。森林浴をはじめとする森林空間の活用に企業が取り組む意義や、森林サービス産業が林業にもたらす可能性について議論された。
-
社会課題解決の切り札となる森林
~脱炭素と生物多様性保全の両立に向けて~2024年10月31日に開催された第2回有識者会議
会議の狙い
幸福度向上にも貢献
長野 麻子氏
モリアゲ 代表
国土の7割を占める森林は、生物多様性の保全、土砂災害の防止、水源の涵養(かんよう)など多面的機能を有している。森林の6割が位置する山村には全人口のわずか2.5%しか住んでいない。これをどう増やすかが課題だ。森林業のモリアゲにより就業・関係人口を増やしたい。
産業界の協力も必要だ。森林は、炭素中立や循環経済、自然再興といったサステナブル経営の同時達成に貢献できるだけではない。森林浴など森林空間の利用により、ウェルビーイング、すなわち個人や集団の幸福度の向上にも貢献しうる。また、木材を利用した空間にも、リラックス効果や免疫力向上効果があることが確認されている。森林のマテリアル利用と合わせて空間利用を推進し、森林業への転換、各企業における社員の心と体を健康にする健康経営に森林を生かしてほしい。

講演
森での体験、人材育成に
小野 なぎさ氏
森と未来 代表理事
林野庁による2021年の森林・林業基本計画では、森林サービス産業の育成や、関係人口、交流人口の拡大を目指すという目標が掲げられている。各地方自治体からは、森林サービス産業にどう取り組んだらよいかという悩みをよく聞く。森林空間自体の価値を上げながら、地域の経済に貢献したい。
一方、都市部では心の健康に不安を抱えている人も多い。都市側で森林と触れ合う機会をつくり、住民の健康増進に寄与したい。
この両面の解決に向け、森林浴を活用した事業を行っている。森林浴は1982年に当時の林野庁長官が提唱した取り組みであり、以来、森林環境が身体に及ぼす健康効果のエビデンスが構築され、関心が高まっている。
当社で力を入れているのが、森林空間を活用した人材育成だ。企業向け、子ども向けなど、様々な世代を対象にプログラムを実施している。企業向けのプログラムでは、健康経営、人的資本経営、環境経営に貢献するものを提供している。森での散策や共同作業を通じ、参加者の幸福度の向上、チームビルディング、働き方の見直し、環境意識を高めることを狙いとしている。各プログラムは、目的や参加者の世代に合わせてカスタマイズしている。
参加者には最終的に森と積極的に関わるようになってほしいが、クライアントの多くは森林とは直接的な接点のない都会の企業である。日常生活で森林と関わりがないと、森の課題が自分ごとになりにくい。森と関わってもらうには段階を踏むことが必要になる。
そこで、まずは森を思うというところから始める。「疲れたから森でリフレッシュしたい」「自然を思わせる、森に関係ある製品を使いたい」といったことからでかまわない。そして、身近な木々と触れ合い、会社の研修などで森の現状や課題について知る機会を持つ。その後、実際に森に出かけてみることで、森の課題に能動的に興味を持ち、森林に関わる取り組みに参加する流れをつくる。
 中でも重要なのが、実際に森に触れる体験だ。体験することではじめて、森林の課題を自分ごととして納得できるようになる。おのおのが納得感を持つと、そこからアイデアが生まれ、自分ごととして関わりたいという意欲にもつながる。
中でも重要なのが、実際に森に触れる体験だ。体験することではじめて、森林の課題を自分ごととして納得できるようになる。おのおのが納得感を持つと、そこからアイデアが生まれ、自分ごととして関わりたいという意欲にもつながる。
当社では、こうしたプログラムを普及させるため、「森林浴ファシリテーター」を育成している。森林浴の活動を通じて、森や地域、関係するすべての人がよりよい状態となれるよう働きかける人材を生み出したい。ゆくゆくはこういった方々も森林・林業従事者に含められることを期待している。

パネルディスカッション
漠然とした価値、見える化を
-
長﨑屋 圭太氏
林野庁
森林整備部長 -
速水 亨氏
速水林業
代表 -
加藤 正人氏
信州大学
農学部 特任教授 -

水谷 伸吉氏
more trees
事務局長 -
橋本 純氏
清水建設
環境経営推進室
グリーンインフラ推進部長 -
堀川 智子氏
中国木材
取締役 会長 -
小野 なぎさ氏
森と未来
代表理事
【モデレーター】
-
長野 麻子氏
参加者の納得感 行動変容につながる
水谷 再造林放棄地など経済サイクルからこぼれ落ちた森林を、企業の出資で再生させる活動をサポートしている。ここで重要なのが、参加する社員一人ひとりの納得感だ。活動には、会社の命で不承不承やって来る方も少なからずいるが、植樹をしていくうちに晴れやかな顔になっていく。「わが社はこんな有意義なことをやっているのか」と腹落ちする、これが行動変容、そして活動の継続に欠かせない。
橋本 群馬県川場村で再造林を行い、森を育ててその木材を当社の案件で使う「シミズめぐりの森」に取り組んでいる。木を植えれば終わりではない、育てる過程でどういった作業が必要かを社員が体験するもので、サプライチェーン(供給網)で自分たちが環境にどういう影響を与えているのか、自分たちが使う木材がどう育てられているかを考えるきっかけとなっている。
今後は、健康経営に組み込む視点も持ちながら、プログラムをつくり上げていきたい。
速水 2020年に国がカーボンゼロの目標を掲げ、また、ネーチャーポジティブ経営を推進するようになったことで、林業を手がける当社にも企業からの問い合わせが増えた。森林に本格的に取り組みたいという意欲を感じている。そこで森林への関わり方、例えば、森林浴的な発想や企業の植林など、先行事例などを紹介しているところだ。
その際に申し上げているのが、一過性の取り組みで終わらせないでほしいということ。樹木は数十年かけて育ち、中には樹齢数千年のものもある。数年で効果が出るものではない。継続することで企業の体質も変わってくる。実際に山を所有して、経営計画を立てることもおすすめしたい。森林や環境をめぐる課題の本質が実感できる。その山で社員研修をしてもいい。
日本発祥の森林浴 海外からも関心
-
 森林浴発祥の地である日本は海外からの関心も高い
森林浴発祥の地である日本は海外からの関心も高い
小野 日本が森林浴発祥の国ということで、海外からの問い合わせが増えている。森林浴を学ぶツアーを組みたい、森林浴の資格が取りたい、ヘルスツアーを組みたいといった要望が多い。公的機関から自国のレンジャーに森林浴のレクチャーをしてほしい、あるいはインターンに行きたいから森林浴を手がけている会社を紹介してほしいという要望もある。日本政府の今後のビジョンを聞きたいというリクエストもあった。ただ、それらに十分に応えられる体制が国内に整っていない。
一方、世界には森林浴に取り組む団体が数多く出現していて、商標を取得する動きもある。アメリカには60カ国に3000人のガイドを育成している団体もあるほどだ。
森林浴の価値を、国内で今一度、見直してはどうか。
加藤 大学で森林情報学を教えているが、若い世代の森林の生態系や環境問題への関心の高さを実感している。地域創生や社会貢献を志す学生も多く、彼らに森林浴や森林浴ファシリテーターのノウハウを伝えていくことで、地域おこし協力隊や森林サービス業の可能性が広がるのではないか。
-
 森林浴発祥の地である日本は海外からの関心も高い
森林浴発祥の地である日本は海外からの関心も高い
土壌の豊かさ測り 指標の一つに
堀川 林業界の者としては、業界外の企業にも森林の価値への評価が広がれば、植林活動も進むと期待している。現状では、山の所有者は苦労して木を植えても、何十年か後に負の遺産になりかねず、植林の意欲が湧かない。森林の保護をクレジット化するなどして実際にお金が動くようになれば、その流れを変えられるかもしれない。
速水 森林運営に投資するファンドを設立したいという相談もあるが、多くは年8~10%のリターンを求めている。ただ、森林に投資する場合、キャピタルゲインはともかく、林業という性質上、毎年のリターンは現状では困難だ。せめて森林価値を基にした方法が確立されると、キャピタルゲインを基にした投資が可能になるのではないか。
水谷 現在のファンドは、木材価格のみが評価軸になっているものが主流だ。森林の空間利用による幸福度向上への寄与、自然再興、炭素中立といったところを評価軸に入れると、森林利活用の可能性が広がる。
長﨑屋 木材利用に関しては建築物への利用の効果に関わる評価項目・方法をまとめたガイダンスが定まったところである。
ただ、清水建設のような企業による森づくりについては、どのように評価するか検討中だ。今年度から、企業戦略として森林整備を行うことを自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)レポートにどう反映させるか、ガイドラインの検討を始めたところだ。
財産としての森林の評価は、一昨年、不動産投資で採用されている手法で森林を評価するガイドライン「DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法による森林評価の考え方とその手順」をリリースした。まずこちらを活用いただきたい。
小野 指標の一つとして、土壌の豊かさを測ってはどうか。土壌に着目されるようになれば、本当に豊かな森をつくろう、そうした森林を所有しようという気運も高まる。
速水 健全な土壌からは、狂いのない木材が生産される。従来型の林業にとっても、土壌で森林を評価する方向性は望ましい。山林の保水能力も上がり、土砂災害防止にもつながるだろう。
長﨑屋 ご指摘の通り、土壌の健全度は重要だ。国土保全の政策や森林の価値に置き換えるには時間がかかるが、重要な視点として捉えたい。
長野 科学技術の進歩により、森林の恩恵を数値化したり、シミュレーションしたりできるようになった。漠然としていた森林の価値がさらに見える化されるようになれば、企業による森林の利活用が進むはずだ。