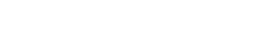- TOP
- 自然再興へ知恵結集 DXで森林活用加速
自然再興へ知恵結集 DXで森林活用加速
森林が生み出す生態系サービスの価値を考え、多くの企業が関わりを持てることを目指し、日本経済新聞社は2024年、2回にわたり有識者会議を実施。その議論を踏まえ12月3日に東京・日本橋で開催した「日経SDGsフォーラム特別シンポジウム 社会課題解決の切り札となる森林」では、DXを駆使した林業効率化や森林浴の効果活用など、幅広い森林活用が紹介された。
基調講演
都市の生物多様性を守れ
久保田 康裕氏
シンク・ネイチャー代表取締役CEO
琉球大学 理学部 教授
地球上には様々な生物が分布している。これら多様な生物は互いに関わり合いながら生態系をつくり上げ、人類に食料供給、空気や水の浄化といった形で、多大な利益、すなわち生態系サービスをもたらしている。豊かな生物多様性は、人類社会の持続に欠かせない自然資本である。
そして現在、人間の開発により100万種に上る野生生物が絶滅の危機にひんしている。この生物多様性の損失を抑止・反転させ、生物多様性の豊かさを取り戻す取り組みがネーチャーポジティブ(自然再興)だ。2030年までに自然再興の実現を目指す国際的な目標「サーティ・バイ・サーティ(30
by
30)」では、国立公園などの保護地域の拡張と管理の質の向上だけでなく、それ以外でも生物多様性保全に資する地域の設定・管理をすることが求められている。
こうした中、我々シンク・ネイチャーは、ビッグデータと機械学習を活用して生物多様性を数値で評価、さらに地図上に可視化する取り組みを行っている。生物多様性には多面的な要素があるため、生物種の数はもちろん、個々の生物種の希少性も「かけがえのなさ度」として数値化し、時空間的な分布を地図として可視化する。
保護区による絶滅リスク低減効果
 @Think Nature, Inc. 2023, All Rights reserved.
@Think Nature, Inc. 2023, All Rights reserved.
そのため、都市部での生物多様性の保全は喫緊の課題だ。人の影響の少ない奥山の国有林だけに保護区を拡大するより、都市部に人と自然が共生する民間保護区(OECM)を設けると、より効果的に絶滅の抑止効果が望めるはずだ。
都市部で不動産開発などの際に森造りを行うことは、30 by 30が求める自然再興のあり方にもかなう。都市での森造りや宅地での植栽にあたっては「在来生物種の生息場所拡大に寄与する」視点から、樹種を選ぶことを推奨したい。
当社では野生生物の分布や相互関係などをもとに、生物多様性ゲインを最大化する植栽樹木の組み合わせを提案するツールも開発している。こうしたデータやツールも活用しながら、科学的なアプローチで計画的に生物多様性再生に資する開発、投資していくことを求めたい。
保護区による絶滅リスク低減効果
 @Think Nature, Inc. 2023, All Rights reserved.
@Think Nature, Inc. 2023, All Rights reserved.
講演
進化する木造建築
池田 明氏
三井ホーム 代表取締役社長
ツーバイフォー工法が日本に導入されて50周年を迎える。同工法は、規格化された構造用製材と釘金物を使用した6面体を構造の基本とする。これにより、地震の衝撃を家全体にバランスよく分散させ、震度7クラスの揺れでも建物の変形や崩壊を防ぐ。この耐震性に加え、高い断熱性、耐火性、耐久性を持つ工法として普及してきた。海外では5、6階建ての大規模集合住宅においてもスタンダードな工法として普及している。
当社はツーバイフォー工法を進化させた独自技術の集合体、「MOCX」を技術ブランドとして用いている。その一つが、高強度耐力壁「MOCX
WALL」である。枠材に高強度の集成材、面材と枠材の接合に独自開発のネジ釘を使用し、壁倍率31倍を実現した。
このMOCX
WALLの使用により、日本初の木造マンション「MOCXION(モクシオン)稲城」の建設に成功した。同物件は、高い断熱性能を示す各種認証、ウッドデザイン賞などを受け、環境的価値の高さを示している。加えて、木造建物としては国内初のエンジニアリングレポートおよび不動産鑑定評価書の取得、国土交通省・令和2年度サステナブル建築物等先導事業の採択による補助金を獲得し、物理的価値、経済的価値の高さを証明した。
こうした技術を戸建てにも導入し、より広い開口部、凹凸の少ないすっきりとした室内デザイン、高い耐震性と断熱性が実現可能になった。また、戸建て用MOCX
WALLには、国産スギの枠材を標準採用し、面材には再生木材を使用することで、脱炭素社会の実現に寄与する仕様となっている。
このほか、大阪・関西万博では大規模空間の木造部分の設計や建築、GREEN×EXPO2027では木造平屋パビリオンを手がけるなどして、多様な建物の木造木質化に挑戦している。一人でも多くの方々に「木で建てれば、街は森になる」という思いに共感いただけたらうれしい。
講演
TNFD開示で前進
橋本 純氏
清水建設 環境経営推進室
グリーンインフラ推進部長
持続可能な社会の実現に向けて、シミズグループは環境経営に注力している。2021年にはグループ環境ビジョン「SHIMZ
Beyond Zero
2050」を策定した。脱炭素社会、資源循環社会、自然共生社会の実現を目指し、まずは自社の事業や施設で、脱炭素、資源循環、自然共生で負の影響をゼロにすることをベースに、社会に様々な価値を提供していく。
環境経営の取り組みの一つが、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)による情報開示だ。当社では、気候変動と同様に自然関連の影響を重要な経営課題と捉え、2023年2月にTNFD提言への賛同を表明し、2024年1月にはTNFD早期採用を宣言している。TNFDに基づく開示の初回である2024年度は、建設、不動産開発、太陽光発電の3事業を対象とした自然関連の財務情報開示を行っている。
開示に当たり、3事業の自然への依存と影響を分析した。原料調達に際しては木材という面で生態系サービスへの依存度が高く、また建設現場での土地の改変や廃棄物の発生と、陸域生態系への影響度が高いことが判明した。前者については、型枠合板に非認証の外国産材が多く使われていることが判明したため、国産材の利用と、外国産認証材による型枠の使用をどう増やすか検討を開始した。2030年までには外国産の非認証材の使用をゼロにする目標を掲げている。後者については、当社独自の自然の状態の把握を実施しながら自然関連リスクを事前に把握して、その回避・低減を図っていく。
森林の利活用をめざし、技術開発も進めている。とくに注力するのが、木造大規模建築を可能とする耐火性や耐震性に優れた木質化技術の開発だ。森を使うことで資源循環、そして森の整備を進めることでの生物多様性にも貢献ができると考えている。
パネルディスカッション❶
スマート化で課題解決
-
加藤 正人氏
信州大学
農学部 特任教授 -
堀川 智子氏
中国木材
取締役 会長
【モデレーター】
-
小原 隆氏
日経BP 総合研究所
社会インフララボ
上席研究員
小原 日本の森林、林業をめぐる課題は何か。
加藤 日本の人工林は1000万㌶あるが、現在、これら人工林を伐採して活用し、再び植林して保育していく循環的な経営が十分にできなくなっている。その原因となっているのが、森林を維持する山村の過疎化、所有者による管理放棄、そして所有者の不明や小規模分散化などだ。
堀川 日本の林業がもうからないことも大きな問題だ。木を伐採して工場まで運ぶ一連の施業コストは、1立方㍍当たり、日本では7120円かかるのに対して、フィンランドは3350円で収まる。
人件費はフィンランドが日本の約2倍だが、1人当たりの生産量が15倍近くあるなどの理由で、こうした差が生まれている。施業コストをいかに下げるかが問われている。
また、山に材はあるのに、国産材の活用は低迷している。日本の木材自給率は、2002年に過去最低の18.8%を記録し、その後、徐々に回復して、2023年には42.9%まで持ち直してきているものの、まだ十分に活用できているとはいえない状況にある。
航空計測やAIを駆使 森林境界の確定を
小原 生産コスト削減を阻んでいるものは何か。
堀川 加藤氏が述べた、所有者が不明、境界が確定できていない森林が多いという問題は深刻だ。効率的な施業のために林道を新設しようとしても、所有者不明な箇所があるとそこに道を通すことができない。
加藤 所有者の世代交代が繰り返されるうちに細分化され、所有者が不明となり、境界が不明となった森林が多い。国の調べでは、林家の9割が保有面積10㌶未満。加えて所有者に連絡がつかない林地は29.8%で増加傾向にあり、林地を手放したい者は33%だ。これらが効率的な森林施業や持続的な森林管理の妨げとなっており、413万㌶の私有林人工林が経営管理不十分の恐れがあるとされている。
効率的な森林施業や持続可能な森林管理への転換を図るため、森林の集約化を進める必要がある。そこで求められるのが、森林境界を画定することだ。これはわが国の社会課題であるといっていい。
小原 具体的な対策はあるのか。
加藤 境界の明確化に際しては、従来は現地立ち会い調査を行ってきたが、所有者の高齢化も進む中、労力的に困難だ。そこで私どもが開発・推進しているのが、ドローン、レーザー計測、人工知能(AI)などを組み合わせて木1本1本の樹種を判定し、林相の境界を自動的に区分して森林境界を推定する技術だ。
2024年度から産学官で連携しながら、長野県の林業拠点地域で実証中だ。国交省が進めている地籍調査でも、こうした技術の活用が始まっている。デジタルトランスフォーメーション(DX)が解決の鍵だ。
データ活用を林野庁も推進
スマート林業で実現する省力化
 小原 急峻(きゅうしゅん)かつ広大な山での植林、保育、伐採、運搬する過程はどういった効率化が可能なのか。
小原 急峻(きゅうしゅん)かつ広大な山での植林、保育、伐採、運搬する過程はどういった効率化が可能なのか。
加藤 林野庁が推進しているのが、地理空間情報などのデータやICT(情報通信技術)、自動化機械などを活用する「スマート林業」だ。先進的な取り組みとしては、カナダの非営利団体FPイノベーションズが示すモデル「FORESTRY
4.0」が参考になるだろう。森林を航空機やドローンを使って立体的に計測し、その膨大なデータをAIが解析して、森林資源の把握や伐採計画、需要と供給の予測、最適な物流計画などでの意思決定を支援していく。伐採や造材、運搬といった現場の施業も、自走式機械を活用して省力化を図る。
こうしたスマート林業を推進していけば、事業体の施業そのものはもちろん、木材の生産(川上)から建築や消費(川下)に至るまでのデータ連携、合意形成、行政サイドの省力化も可能となる。林野庁では2028年度までに、スマート林業を意欲と能力のある林業経営者に定着させることを目指している。同庁のサイトではスマート林業に関する情報発信が行われているので参考にされたい。
私ども信州大学と精密林業計測も、スマート林業の実現に向けて様々な実証事業を行っている。その一例が、複合現実(MR)技術を使ったヘッドセット、マイクロソフト社のホロレンズの活用だ。現場作業員が着用したホロレンズに苗木を植える場所を投影して、任意の場所まで誘導し、植林作業などをサポートするものだ。植林後の下刈りの際も、苗木を植えた場所を投影すれば、小さな苗木の誤伐を防ぐことができる。この技術は自走式の林業機械にも応用可能なので、夏場の過酷な下刈りもいずれは自動化できるだろう。
 スマート林業で実現する省力化
スマート林業で実現する省力化
利用機運を高め 所有者に利益還元
ホロレンズ装着による誘導植栽
 提供:精密林業計測、北信州森林組合
提供:精密林業計測、北信州森林組合
小原 森林の所有者に利益が還元される仕組みづくりも必要だ。
堀川 まずは国産材を利用する機運を高めたい。日本のスギやヒノキは、よく使われている欧州材と比べて耐シロアリ性や耐久性に優れているのに、これまで適正な評価を受けてこなかった。施主の方々には、スギやヒノキを使いたいと工務店やビルダーにリクエストしていただけると、林業界としてはありがたい。
森林や木材の活用は二酸化炭素(CO2)排出量の削減や、ネットゼロ達成に重要な役割を果たす。例えば、木造建築は鉄筋コンクリート建築と比較して、炭素貯蔵量が約4倍あり、製造時のCO2排出量は約4分の1にとどまる。こうしたことから、非住宅の建築でも木造が増加しており、倉庫、商業施設、体育館、駅舎、大規模建築物でも採用が進んでいる。また、木造建築は、重機が入れない狭小地や軟弱地盤など、従来の工法では建設が困難な条件下で有効な解決策となっていることも知っていただきたい。
併せて、林業や製材加工側の体制整備も進めていくべき。業界全体で国産材の安定供給や規格の統一を図り、需要に的確に対応できるようにしていきたい。当社でも、大型製材工場や物流ネットワークを全国に構築しているところだ。
小原 持続可能な森林経営には再造林が不可欠だ。しかし、日本の再造林率は3、4割程度と低迷している。その重要性を、山林所有者はもちろん社会全体で共有していくことも必要ではないか。
堀川 木は樹齢を重ねるとCO2吸収量が低下する。気候変動対策の意味でも、適切な伐採と再植林は重要だ。また、土砂災害防止のためにも適切な森林管理は欠かせない。再造林を社会全体で支援する仕組みがほしい。
再造林が進まない主な理由は、林業の収益性の低さと将来性への不安だ。国産材の活用のほか、炭素吸収量を取引するJ―クレジット制度などが森林管理の新たな資金源になるものと期待している。
ホロレンズ装着による誘導植栽
 提供:精密林業計測、北信州森林組合
提供:精密林業計測、北信州森林組合
森林の価値を再発見
講演
森林浴、世界から注目
小野 なぎさ氏
森と未来 代表理事
日本は、木を売るだけでは森林を維持できない状況に陥っており、現在、様々な対策が講じられている。2024年から森林環境税が導入されたほか、国の森林林業基本計画では、森林空間そのものを活用して、山村地域で経済価値を上げていく取り組みが推奨されている。森林空間を活用した体験サービスなどを提供することで、人々に健康で心豊かな生活をもたらし、企業で働く人の活力を向上させ、山村地域に新たな雇用と所得機会を生み出すことを目的とするものだ。これを林野庁では「森林サービス産業」と呼んでいる。
森林サービス産業の一つとして、今、国際的にも注目されているのが森林浴だ。当社も企業などを対象に、森林浴体験を通じて地域経済に貢献しながら、森から離れて暮らす都市の人々に森に行く機会を提供している。森と触れ合いたいというニーズを満たし、参加者の健康の向上に貢献するとともに、森林の現状や課題を伝え、自分ごととして関わりを持つ機会を提供することを意図している。そのほか、健康経営、環境経営、人的資本経営の参考となるプログラムも実施している。
そもそも森林浴は、1982年に、当時の林野庁長官によって命名・提唱されたものだ。森の中にはフィトンチッドと呼ばれる殺菌作用を持つ揮発性成分が存在し、森の中にいるだけで健康に資するとして始まった取り組みである。
その後、医学分野でのエビデンスが積み重なり、論文や書籍で発表され、海外でも森林浴という言葉を横文字にした〝Shinrin‐Yoku〟、あるいは英訳した〝Forest Bathing〟という言葉が普及していった。いまや各国で森林浴の研究をしている団体や森林浴ガイドの育成を行っている団体が出現しており、米国には6大陸60カ国で3000人ものガイドを育成しているところさえある。
森林浴が日本発祥の取り組みとして知られていることから、日本で森林浴を体験したい、という海外からのニーズも高い。当社にも様々なリクエストが寄せられており、コロナ禍が明けた2023年から、ジャパン森林浴ツアーを開催し、森林浴を学んでいる方々を世界から招き、日本の森林浴を体験していただいている。
海外の方に日本の森林浴を紹介する際に必ず説明しているのが、日本人と森の精神的・文化的な関わりである。山にある鳥居は、山が地域の人々にとって神聖な領域であることを示すことや、伊勢神宮の式年遷宮のために、数百年単位でヒノキを育てる森があることなど、文化的な背景、価値観を含めて日本の森林浴の魅力を伝えていきたい。また、それができる人材の育成も始めている。
-
森林浴を学んでいる外国の方々を招き日本の自然観を伝える

日本発祥の森林浴は海外からのニーズも高い(岐阜県高山市・写真上)
文化によって森林との関わり方は異なる。互いの文化や価値観を共有することも重要(写真下)
-
 © 2024 Future with Forest Inc.
© 2024 Future with Forest Inc.
日本発祥の森林浴は海外からのニーズも高い(岐阜県高山市・写真上)
文化によって森林との関わり方は異なる。互いの文化や価値観を共有することも重要(写真下)
パネルディスカッション❷
産業界で森の未来守る
-
小坂 善太郎氏
林野庁
次長 -
速水 亨氏
速水林業
代表 -
水谷 伸吉氏
more trees
事務局長
【モデレーター】
-
長野 麻子氏
モリアゲ
代表
長野 森林が日本の国土の7割を占めるのに対し、森林の6割が位置する山村には全人口のわずか2.5%しか住んでいない。そのため、先人たちが育ててきた森林が管理不足で持続不可能になりつつある。都市に暮らす人々はこれを他人ごととしてはならない。
森は木材の生産地であるとともに、多様な生物の生息地であり、水源を涵養(かんよう)し、土砂災害を防ぐ機能も持っている。森林なくしては、農業も商工業も成り立たない。さらに森林は、カーボンニュートラル、循環経済、自然再興、ウェルビーイング(心身の健康と幸福)の向上など、現代社会の重要課題を同時達成できる解決策となる。
日本で私たちが安心して幸せに暮らしていくために、森林の保全は非常に重要な課題である。企業の森、企業版ふるさと納税など、企業として貢献可能な方法は数多くある。ぜひ産業界のお力添えをお願いしたい。自社にできることを、自分ごととして考えていただきたい。
小坂 戦後、荒廃した国土に先人たちが木を植え、その森林を守ってきたおかげで、1000万㌶の人工林が築かれるとともに、2500万㌶の森林が保たれてきた。世界的に森林減少が起きている中、これは誇るべき状況と思う。ただ、木材価格は1立方㍍あたり、1980年のピーク時の2.2万円から、現在は4000円と5分の1に下落し、再造林のコストが収入を上回る状況となっているなど林業界の状況は極めて厳しい。
先ほど長野氏が述べたとおり、森林には多面的な機能があり、我々の生活に深く関わっている。今後も適切な整備・管理ができるように、国としても環境を整えているところだ。
気候変動対策としては、2030年までに森林で2.7%の炭素中立をカバーする目標があり、森林の適切な伐採・再造林による若返り、木材の利活用による炭素の長期貯蔵、エネルギー利用などを推進している。生物多様性の保全については、30
by
30や企業活動のTNFD情報開示など国際的な取り組みが進んでおり、林野庁も生物多様性を高めるための林業経営指針を策定している。
産業界には、排出量削減や炭素吸収量を取り引きするJ―クレジットの活用や、木材を積極的に活用するウッドチェンジ、企業の森造りなどに取り組んで、森の未来を守っていただければ幸いだ。
環境対策の位置づけ CSRから本業へ
水谷 我々more
treesは、都市と森をつなぐことを目的とし、全国22カ所で森林包括協定を結び、企業などと協働しながらJ―クレジットの創出、国産材利用、植林・育林活動などを展開している。
伐採後の再造林放棄地の問題に対しては、奥山など生産に適していない場所には広葉樹を植えるなどして、人手をかけずに維持できる森を造っている。植林に当たっては、地域の気候風土に合った多様な樹種を選定して、生物多様性保全に配慮した森造りを進めている。
その際は、企業からの出資を募るだけでなく、現地での苗木作りや植林に実際に参加いただくなどして、企業の方々、そして地域住民を巻き込みながら、森を基軸とした関係人口を創出していくことを意識している。
長野 森造りに参加する企業の意識も変わってきているのではないか。
水谷 従来は化粧品メーカーやアパレル業界といった消費者と接点の多い企業がCSR(企業の社会的責任)活動の一環で参加する傾向があった。加えて近年は、金融やIT(情報技術)といった、森林とは接点がなさそうな業種からの参加も増えている。企業の森づくりの担当部署が、CSR部門からマーケティングや販促といった本業に近い部門にシフトしており、かける予算も大きくなっている。環境対策がより事業戦略の中核に位置づけられるようになってきていることを感じる。
そのほかにも、森造りの活動はESG(環境・社会・企業統治)投資対応、採用活動、顧客とのコミュニケーション、学生インターンの受け皿など、多様な企業活動に活用されている。
小坂 J―クレジットの活用や企業の森造りについては、林野庁にも多くの問い合わせがある。気候変動や生物多様性への国際的な関心の高まりにより、環境や生物多様性への貢献なしには国際社会で伍していけないという意識が高まっているのだろう。
多面的価値を評価に上乗せ
森林由来J−クレジット認証量の推移(累計)
 出典:J-クレジット制度事務局ホームページ掲載情報より林野庁森林利用課作成
出典:J-クレジット制度事務局ホームページ掲載情報より林野庁森林利用課作成
ただ、林業を採算ラインに乗せるのは簡単なことではない。まず難しいのが、森林の買い取り価格の判断だ。これまでいろいろな評価の仕方があったが、今後は企業会計の中で通用するような森林価格の算出法が求められる。森林の価値や採算性をどう評価するか、新たな課題となってくるだろう。
長野 算出する木材の品質や環境価値まで経済評価に上乗せできるような手法はないのか。
小坂 森林の多面的価値をもっと評価していく必要性は認識している。CO2削減についてはクレジット化が実現し認証量が増え続けている。Jークレジットなどによる排出量取引については、2026年から取り組みが本格化される予定だ。生物多様性の保全や森林浴などの森林サービスへの取り組みをどう評価するかだが、こちらについては今後の課題だ。
水谷 英国では不動産開発を行う際は、生物多様性ネットゲイン10%が義務付けられることとなった。こうした国際的な動きに我が国も追随する可能性がある。不動産業界や建築業界は注視しておきたいところだ。
また、環境省の自然共生サイト制度が拡充され、森林を回復させる取り組みも認定対象となる予定だ。当面はこうした認定を受けることが森づくりのモチベーションとなるのではないか。
速水 注意したいのは、日本の認定制度は、国際的な基準に照らすと厳密性に欠ける面が少なからずあることだ。行政サイドが認定数を増やすことに注力しがちなことも一因かもしれない。国際的に通用する認定制度を目指し、厳しい審査基準を設けてほしい。国際競争をめざす企業にとっては、厳しい基準の認定こそ価値がある。
長野 かつては地元の名士や素封家が山を所有し、投資して森を育てていた。しかし現在、その流れをくむ林業家は苦境に立たされている。森造りが可能なだけの財力があるのは、やはり企業ではないだろうか。
森林由来J−クレジット認証量の推移(累計)
 出典:J-クレジット制度事務局ホームページ掲載情報より林野庁森林利用課作成
出典:J-クレジット制度事務局ホームページ掲載情報より林野庁森林利用課作成
木を植える動き 企業の誇りに期待
速水 伐採が終わった土地の6割が再造林できないという状況は、先進国として残念な状況だ。企業の内部留保は約600兆円あると聞いている。その1%でも森林投資に活用されると、状況は劇的に改善する。内部留保の1%とまでいかなくとも、50万円あれば1㌶の植林が可能だ。これは決して無理な金額ではない。企業が「森を守る」という誇りと気概を持って全国で木を植える動きが広がってほしい。
各企業がどれだけ木を植えたかをデータを出してはどうか。林業界も投資を呼び込むためには、説明責任と透明性を確保することが必要だ。
小坂 水谷氏から奥山に広葉樹を植えて自然に委ねる取り組みの紹介があったが、そうしたゾーニングは重要だ。林野庁としては日本の人工林1000万㌶のうち、林業として条件の良い3分の2の660万㌶を循環利用し、残り3分の1は自然に戻すことを方針としている。
また、森林の用途や生息する生物の多様性を確保するために、市町村を超えた都道府県レベル、流域レベルでグランドデザインを描き、適切にゾーニングしていくことが必要だろう。それを念頭に、民有林と国有林の連携も強化しつつある。もちろん、地元の理解は不可欠であり、企業が森林投資を行う際も、地域の森林組合や事業体とパートナーシップを組み、地域と共に森林管理を進めていくことが重要だ。
水谷 国際的な動きを踏まえ、企業には業界内で森林保全にいち早く取り組む「ファーストペンギン」となってほしい。先駆的な取り組みを行うことで、脱炭素、採用、マーケティングなど多面的な価値を創出できるはずだ。森林のうまみをとことん吸い出そうという貪欲さがあっていい。
長野 森の価値のデータ化が進むようになったことで、森への投資の効果もまもなく可視化されるようになるだろう。100年後を見据えて、まずは一歩踏み出していただきたい。日本の産業、文化、自然を維持できるのは森林があってこそ。自然資本の担い手として、企業には大いに期待したい。