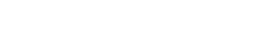- TOP
- 流域連携で価値高めよ
日経 グリーンインフライニシアチブ
森林価値創造プロジェクト
第1回 有識者会議
流域連携で価値高めよ
日経グリーンインフライニシアチブ「森林価値創造プロジェクト」第1回有識者会議が6月20日、都内で開催された。今回、森林の価値を創造するキーワードとして「流域」という概念が登場。森林機能の定量化の必要性が議論された。(肩書は開催時)
開催にあたって
運命共同体の意識醸成
長野 麻子氏
モリアゲ 代表

持続可能な社会の成立に欠かせないのが、炭素中立、循環経済、自然再興、そしてウェルビーイング向上だ。これらを同時に達成できるのが国土の7割を占める自然資本である森林だ。中山間地域の人口減少が進む中、森林の価値を継続的に高めていくには、河川の流域単位での連携が極めて重要となる。上流の山間部と下流の都市部を水という共通項で結びつけ、流域圏のつながりを可視化し、具体的な連携に発展させる必要がある。上流の森の整備が下流の水利用を安定させるという、運命共同体意識を醸成していきたい。
流域連携の概念は古くからあり、現在も多様なアプローチが模索されている。愛知県安城市では水源の森が下流域の生活を支えるという考えの下、約30年前から長野県根羽村の分収育林事業の費用を支えてきた。近年は森林環境譲与税を活用した上下流連携の動きが全国で広がり、譲与額の少ない小規模自治体でも広域連携によって大きな効果を得られる点が注目されている。四国では水源の高知県土佐町、本山町と利水域の高松市が連携して基金を設立し、森林整備などに充てる動きもある。こうした取り組みの広がりから森林への経済的な循環が生まれ、持続的な森づくりの進展が期待される。
講演
水循環、企業も貢献を
沖 大幹氏
東京大学 総長特別参与・
大学院工学系研究科 教授

豊かな水の利用のためにはなにが必要か。森林もその一つに挙げられるが、水を蓄えるのは木そのものではなく森林土壌である。森林土壌に染みこんだ水が、地下の基岩に染みこみ地下水流へ送られる。雨が降っていないときにも水が流れているのは基岩にたまっている水があるからだ。森林土壌が失われると雨水はすぐに川に流れ込み、基岩に蓄えられなくなる。
「水みんフラ」とは水に関する社会共通基盤全体を指す言葉で、ダムや堰(せき)、水道管、農業用水路などの構造物(インフラ)、森林や湿地などの自然環境、そしてそれらを管理する人や組織を含む。それらは三位一体であり、一つでも欠けると水資源の安定供給は難しい。
日本の水みんフラが綻びつつある。インフラでは耐用年数40年を超えた水道管が全体の20%以上といった老朽化問題や、水管橋の崩落などの不具合が発生している。また自然環境の劣化や組織の人手不足も深刻で、必要な維持管理ができていない。

水みんフラが支える健全な水循環
日本は今、健全な水循環を確保するため「流域総合水管理」へとかじを切っている。これは川の流域全体を1つの単位として、水の利用と環境保全、災害対策を統合的に進める考え方だ。
都市部だけでなく、山間部や農村地域も含めて流域全体で水を守るためAI(人工知能)やデジタル技術も活用する。行政はもちろん企業や市民、地域団体などあらゆる関係者が連携し、役割を果たすことが求められている。
 水みんフラが支える健全な水循環
水みんフラが支える健全な水循環
パネルディスカッション
評価モデル構築し森づくり促進
-

長﨑屋 圭太氏
林野庁
森林整備部長 -

速水 亨氏
速水林業代表
-

加藤 正人氏
信州大学
農学部 特任教授 -

水谷 伸吉氏
more trees
事務局長
【モデレーター】
-
長野 麻子氏
長野 林業の現場では、森林の流域への影響をどのように意識、対策しているのか。
速水 30年前まで尾鷲地域の林業では、1㌶あたり1万2000本もの密植を行っていた。林地は真っ暗で下草が生えず、土壌が流出しやすい状態だった。そこで速水林業では伐期を長くしながら木の成長を促すため、積極的に間伐を行って下層植生を維持しながら土壌に有機物層を形成させた。消防車を借りて降雨実験を行い、下層植生の有無による土壌の流出量についても実験している。その結果、下層植生が豊富であれば土壌の流出はゼロになることが判明した。
現在気になっているのが、日本全国の山林で高密度作業路が張り巡らされるようになっていることだ。間伐の目的の一つが土砂流出を防ぐ下層植生を育成することなのに、そのために作られた作業路からの土砂流出量は無視できないほどの量だ。作業路からの土砂流出をどう抑えるか、研究や指導が必要だ。
長﨑屋 2020年に年に熊本県南部で起きた豪雨による山腹崩壊事例を調査したところ、急傾斜や凹地形といった自然条件に高密路網の作設といった人為が重なった場合に崩壊が多くみられており、高密路網の作設の際には現場の地形に特に注意が必要だ。
長野 森林科学や森林の水の循環を研究する森林水文学などではこの問題をどう捉えているのか。
加藤 これまでは林業現場の効率化をどう進めるかが大きなテーマで、その手段の一つが作業路の増設だった。作業路が治水という観点からでは負の側面もあるという指摘は、新たな着眼点となる。
沖 林道や登山道からの土砂流出については、森林水文学の特に砂防系の研究者が懸念してきたところだ。対策については、森林研究・整備機構などが森林作業道からの土砂流出を抑える方法を提案している。一部の登山道では土砂流出を抑える工夫が施されるなど、すでに対策が講じられている。ただし、土砂の流出量を間伐の効果と合わせて総合的に評価するには至っていない。
加藤 信州大学と精密林業計測で開発しているドローンや航空機によるレーザー計測であれば、広範囲の森林を3次元的にスキャンし、下層植生や地形まで把握できる。人工林の水源涵養(かんよう)機能の評価に組み込むことが可能だ。
適正な土壌の保全が必要
長野 林野庁はこの問題にどう取り組んでいるか。
長﨑屋 土壌が保全されてこそ、森林の水源涵養機能が果たされるという意識を持っている。その他の機能や生物多様性への影響も大きい。森林の維持・管理には、土壌を考慮する必要があり、作業道や登山道の管理もその一環となる。
土壌の保全を適正に推進するために欠かせないのが、水源涵養機能の定量化である。これは容易ではない。二酸化炭素の吸収量であれば木の成長量を基に算出可能だが、水は地下に蓄えられるので視認できない。植生よりも地質や地形などの影響が大きい点もネックになる。とはいえ、SDGs(持続可能な開発目標)や自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)といった企業の取り組みが進むなか、水という視点での評価も今後は必要になるだろう。
森林づくり活動の評価に資するよう、水源涵養量を数値化する研究を3年がかりで進めてきた。具体的な内容は今年度中に発表予定だが、森林の降雨量から河川への流出量と木の蒸発散量を差し引いて、地下に蓄えられた水を推定する。簡便に取り組めることも特長である。
それ以外にも、土壌がどの程度保全されているか、下草が豊かになったか、落葉層が増えたかといった活動の結果も併せて評価することで、より説得力が増すと考えている。企業が森づくりを進める際の多面的な効果の評価法は、今後も検討を重ねていく。
間伐を考えた数値化も
沖 森林ごとに涵養量を数値化する試みは素晴らしい。さらに、その結果が十分でなかった場合に、どのようなアクションを取ればよいのかも定量的に示せれば、企業の投資判断にもつながりやすい。例えば、この面積の森に対して、どの程度の間伐を行えば、涵養量がどれだけ増加するかといった具体的な数値が示せるとよい。
長﨑屋 まさにその実現を目指している。水そのものを測るのは困難なので、最終的には土壌の状態を見ることになるだろう。間伐によって樹冠疎密度が低下し、下草が増えるといったデータはすでにあるので、そういったものを指標として活用し具体的な施策へとつなげていきたい。
長野 more treesは企業の森づくりをサポートしているが、活動の成果はどう評価しているのか。
定点観測で成果を分析
水谷 定量的な評価の活用はいまだ発展途上にあるものの、その必要性は強く認識している。近年では企業だけでなくNPOにおいてもインパクト評価を求められるようになった。預かった資金をどのように活用して成果や社会的影響をもたらしたか、客観的な評価が求められる。
国際的なイニシアチブであるTNFDなどではカーボンだけでなく水の安全保障(水セキュリティー)が重視されるようになり、水災害など水リスクに対する意識は確実に高まっている。生物多様性や水についても、定量的あるいは定性的に評価できるよう情報収集を進めている。
土壌分析を行っている研究機関もあるので、林地の複数箇所で土を採取して分析を依頼すれば、水源涵養機能や土壌の肥沃度をある程度評価できるだろう。定点観測を続ければ、企業の取り組みがもたらす変化を確認できるはずだ。
長野 各所の研究の積み重ねで、評価モデルが構築されつつあることは喜ばしい。実際のデータが加われば、精度も高まることだろう。今後は現場での実装と学術的なフィードバックを繰り返し、データを活用しながら、自然への理解を深め、さまざまなスケールの活動につなげたい。